考えるヒント
マサ 文
セスの本は出版された順序で読むのが望ましいとされています。これは、セスがおおむね前の本の上に積み重ねるように話を進めていくためです。このため、出版順に読んだ場合でも、前の本が理解できていなかったら次の本を理解するのも難しいでしょう。
この記事ではセスの本をよりよく理解するためのポイントを考えてみたいと思います。英語でいえば“hints”ではなく“tips”ですが、わたしが若かったころ(遠い目で…)あこがれていた小林秀雄さんの「考へるヒント」へのオマージュとしてタイトルを拝借しました(もちろん、内容は比較になりませんが…)。
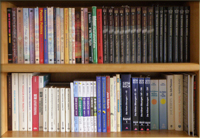
では、まず自分がセスの本をどのくらい理解しているのかチェックする基準を考えてみましょう。
読んだ本に対する理解度には
- 本を読んだことは覚えているが内容は覚えていない
- 内容は何となく覚えているがほかの人に説明はできない
- 具体例を挙げて内容を自分の言葉で説明できるし、実践もしている
など、いくつもの段階があります。また、自分自身の理解度がわかっていないこともよくあります。「この本を読んだ」=「この本を理解した」と考える人も珍しくありません。ひどい人になると、それ以前に本を買ったことすら忘れて同じ本を2冊買ってしまったりします(わたしのことですが…)。
では「理解する」とはどういうことでしょうか?
「わかる」ということ
たとえば、子供に足し算を教えたとします。
1+1=2
2+3=5
という具合にいくつかの例を示したあとで
4+1+2=
という式を見せます。
足し算の意味を理解できた子供なら自然に答えが出てくるでしょう。逆に、ここで答えが出てこなかったら、理解できていないことになります。

道案内にしても同じです。
「駅へはどう行けばいいですか?」
と聞かれたとき、その駅の場所と道順がわかっていれば答えの方から勝手に出てくるでしょう。物事を理解しているかどうかは、この「正しい答えがおのずから出てくるかどうか」ですぐにわかります。セスの話に即した例を挙げるなら、
「あなたがこれまで生きてきたなかで蓋然性(確率的偶然性)の大きな分岐点を挙げてください」
と尋ねられた場合、「蓋然性(確率的偶然性)」という概念自体が理解できていなかったら、答えたくても答えようがありません。

